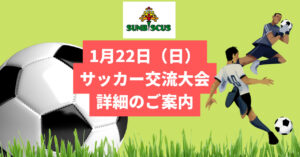明けましておめでとうございます!
2023年、僕の1記事目となります。
今年も皆さんにとって、お役に立てる記事をお届けできるよう頑張りますので、よろしくお願いいたします。
さて、宣言したばかりなのですが、少し個人的な話をさせてください。笑
昨年の8月に生まれた第1子の愛娘も、早いもので5ヶ月となります。
現在は首が座り、食事もミルクから離乳食に少しずつチャレンジ中です。
また寝返りもできるようになったのですが、まだ仰向けに戻ることができないため、しばらくすると、「ママ、パパ、たすけてー」と泣いて助けを求めてきます。笑
脳が成長しているサインの寝言泣き(子育てして初めて知りました。)も始まり、夜中に何度か突然大声で泣いて、驚かされる日常を過ごしています。
ありがたいことに、順調に元気に育ってくれているのかな。
そのように思います。
これまでの日々を、たまに妻と成長記録の写真を見るのですが、本当にひと月ごとに体のサイズや顔つきも変わっていく姿を見ていると、
成長の嬉しさと一緒に、もう戻らない日々を思い返して、なんだか少し哀しい気持ちにもなってしまいます。
なので子どもが大きくなったときに、あの時、、、こうしておけばよかった。
そう後悔しないように、できるだけ抱っこしてあげたり、一緒に関わる時間を作りたいなと思い日々を過ごしています。
そんな初めての子育ての中で感じることは、できないことが日々できるようになる凄さです。
昨日できなかった寝返りが急にできるようになったり、物を目で追えるようになったり、僕や妻の顔を認識できたり、その分、人見知りが爆発中(笑)ですが、みるみる成長する姿に、人間って凄い生き物だなぁって子育てをすると感じます。
その中で、運動指導においても通じることにも改めて気づきました。
それは、「できない」ことを前提で考えることの重要性です。
子育てをしてきた皆さんなので伝わると思うのですが、赤ちゃんと関わるときは、「できない」を前提に物事を考えますよね?
1人で着替えることも、ご飯も、いろんなことができない状態から、保護者の皆さんは自分の時間を削り愛情を持って尽くしていくことで、月日をかけて「できる」ことが増えていきます。
例えば、僕らも初めからお箸を上手く使えなかったはずです。
まずはわし摑みから始まりお箸がどんなものかを感覚で掴み、次のステップとして正しい握り方を教わり、少しずつ慣れながら今のように上手に扱えるよになったと思います。
たくさんの経験を行っていくことで感覚が磨かれ自分のものにできるというステップがあるということです。
つまり、「できない」から「できる」の間にあるものを何かと考えた時、それは「感覚」なのだと思うのです。
特に運動能力を上げるとされている神経系は、12歳までにほぼ100%完成します。
なんなら保育園や幼稚園を卒園する6歳時点で、大人の90%の神経の発達と同じになることを考えると、この時期に神経系を育むことって、とても重要なわけです。
その上でこの期間に必要なことは、たくさんの色んな動きをさせてあげることだと言われています。
キッズスポーツでいろんな動きをしているのは、この事が理由になります。
なので神経回路を作っている段階の子ども達にとって、できないではなく、まだ感覚がないと考える方がいいと思うのです。
できないというマイナスイメージで物事を捉えてしまうと、できないことにイライラしたり、無意識にできることへの期待を抱いてしまいます。
そもそも神経からすると、「いや、そもそも投げるっていう動作の感覚がまだないねん!」って思っているかもしれません。笑
なので、できないことを前提に、いろんな動きをさせてあげて、まだ体験したことがない感覚を経験させて感覚を養っていくという暖かく見守るような考え方が、特に幼児期においては大切だと思うのです。
新しい1年も、今関わっている子どもたちを始め、きっと様々な出会いがあると思うので、今まで体験したことない運動で、子どもたちの感覚を刺激して育んで、たくさんの「できた」の成功体験を与えたいと思います。
感覚という大きな幹に、たくさんの体験という枝を生やして、たくさん経験させてあげることで花を咲かせられるように関わりたい。
そう思います。
いい感じの言葉で締めることができたので、新年最初のブログはここで終わりたいと思います。笑
今年も一年、どうぞよろしくお願い致します。